
いすゞ製作所
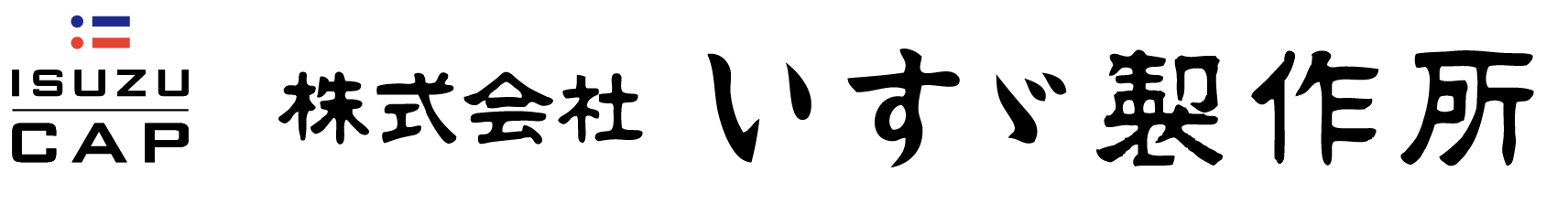
基本理念
人に優しく、地球に優しい製品作り
事業内容
昭和13年に気象観測機器の製造販売から始まり、汎用科学機器の製造販売を経た事で培った「温度・湿度」に関して独自の技術を生かし、測定機器としての機能を考慮した製品開発、製造販売を行っています。激変する時代の中で必要とされている試験環境・性能へのご要望も多種多様かつ複雑化しています。私たちメーカーの使命はそのような社会から要求される製品作りを行うことです。
CARBONIXを導入したきっかけ
いすゞ製作所では「環境試験機」という、さまざまな温度・湿度の環境下で信頼性評価試験を行う装置を製造、販売しております。
納入先は自動車関連・家電・薬学・医療関係・官公庁など幅広く、最先端の企業の開発にかかわっており、現在SDGsの観点からも、製造業が認証を受けているISOも、すべてのマネジメントシステム規格に「気候変動への配慮」を盛り込む追補改訂を行い、要求事項に取り入れらておりますので、脱炭素や電力削減というのは避けて通れません。
もともと弊社の、企業としての考え方やものづくりに対しての思いに「人に求められ、地球にやさしい製品づくり」というものがあります。
この考え方がGHG削減とつながり、CARBONIXと合致していたため、説明を聞くことにしました。

CARBONIX導入への障壁
説明を聞くにあたって、最初に資料をいただいたのですが…。
「専門用語満載で、何が書いてあるのかわからない」というのが正直な感想でした。
アルファベットで省略されているものが何を指しているのかもわからず、一つずつ調べて理解するところから始めました。
その後契約してから、資料の動画を見て調べつつ進めていたのですが、時間がかかるのでこれでは前に進まないと思い、とにかく実際にやってみようとデータ登録の作業をスタートしました。

CARBONIXを使うなかでの発見
弊社ではフロン系のガスを取り扱っているのですが、事務系ではそれらに触れる機会もありませんでしたので、CARBONIXの入力をするようになって「フロン」にもたくさんの種類があることを知りました。
混合フロンを知ったのもCARBONIXがきっかけです。
データを入力するなかで、フロンがどういったもので構成されているのか、どのような割合で構成されているのかを知ることができました。
「二酸化炭素排出削減」という言葉は頭の中にあっても、いざ深掘りしていったときにどういったものを削減すべきなのかというのを改めて学べたのが大きな発見ですね。
GHG算定をするにあたっての苦労
最初は「HFC(ハイドロフルオロカーボン)って何?」というのを実際に扱っている担当者にヒアリングするところから始めました。
どのような種類を扱っているのかを聞き、CARBONIXのシステムのなかではどの選択肢に当たるのかを探し出す。
というように、GHG算定のためのデータ入力に辿り着くまでに何段階かのステップがあるため、達成感がありますね。
必要な情報を集めるために社内の各担当者とオンラインでやり取りを重ねるのですが、なかなか必要な情報を引き出せず苦労しました。
しかし最近ではスムーズに情報を集められるようになり、毎月のGHG算定をスルスルと進められるようになりました。
CARBONIXを活用し始めて変わったこと
消費電力ついては、弊社では製造現場の装置もありますので、経費的にも大きな課題となっております。
CARBONIXを活用しGHG算定をするようになり、電気料金に対して排出している炭素の量がわかるため、2つの側面から「減らさなければ」という気持ちが強くなりました。
そのため、今年の夏からは今まで以上に節電を心がけ、社内に対しても呼びかけています。
GHG算定に携わっていると「節電はまず自分から!」と、不要な電灯やエアコンを消すなど、積極的に節電の行動を起こすようにもなりました。
そういった行動が、これから数値にどう現れるのか、見るのを楽しみにしているところです。
CARBONIXを使い続けようと思った理由
CARBONIXの1年間の無償提供期間が終了し、そこで使用をストップするか有償に切り替えるか…となったときに、CARBONIXを更新しなかったらどうやって炭素の計算をするのか、と考えまして。
GHG算定の係数も時折変わりますし、それを自分たちで計算しながらグラフ化するのは大変だろうと考えました。
また、GHG算定を続けることで、社内に対して脱炭素や節電に対して啓蒙できるのではないか考えたのも継続したひとつの理由です。
脱炭素についての社内勉強会の実施など、社内に脱炭素の意識を広める活動をするときにも、CARBONIXのアシストが必ず必要になると思い、活用させていただいております。
サステナブルリンクボンドを検討するきっかけ
新潟の県央地区である三条市・燕市・加茂市で初めてのサステナブルリンクボンドを発行してみませんか、という提案をいただき、今年の7月に発行しました。
せっかくCARBONIXを活用して炭素の計測をしているので、それが役に立ち、私たちにとってもメリットがあるのであればと考えたのがきっかけです。経営的に判断し、発行するメリットが大きい為、発行の決断にいたりました。
発行に先駆けて、CARBONIXでGHG排出量算定はもちろん、SDGs 宣言を行うことで社内の現状把握と今後の目標設定を明確にしました。
当地の商工会議所などでも、脱炭素に向けてこれから勉強会を開こう、という動きがあり、先駆けてサステナブルリンクボンドを発行することができたのは、非常に価値が高いのではないかな、と思っております。
GHGの見える化の意義
CARBONIXの活用やサステナブルリンクボンドの発行、そしてSDGs宣言といった取り組みは
「地球」「働く人」「地域」「お客様」のすべてにとってプラスとなるように、目標を設定して行っている活動です。
漠然と登録してますよ、宣言してますよ、というだけではなく、目標を持って数値化するのが大切だと思っています。
数値化して、誰が見てもわかるようにしないと、評価はされませんよね。
そして、数値化することでさらに目標が明確に設定できるようになります。
自分たちの行動を自分たちで評価できるようになるのが、非常に大事なことであると思っております。
今後のカーボンニュートラルに向けた取り組み
弊社は10年ほど前から節電に励んでおり、全館LEDに切り替えるなどすでにさまざまな節電対策を実施しています。
使う電力を減らすには限りがあるため、次は使う電力を生み出すために太陽光発電の導入を検討しているところです。
また、製造現場の設備を新しいものに変えて、電力消費を抑えるということ、自社での太陽光発電を視野に入れてすでにプロジェクト始動しております。

