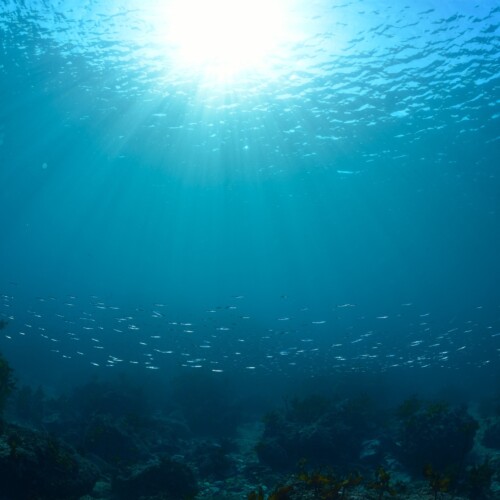水リスクが企業経営を左右する?取水制限・価格高騰・評判リスクの実態と対応策

水は、人々の暮らしや産業活動に欠かせない根源的な資源であり、農業や工業、エネルギー生産、衛生など、社会・経済のあらゆる分野で利用されています。しかし、その供給量には限りがあり、近年では、気候変動による干ばつや異常気象の頻発、人口の急増、経済発展に伴う水需要の増大などを背景に、世界各地で水不足や水質汚染といった「水リスク」が深刻化しています。これらのリスクは、水資源へのアクセスだけでなく、食品安全保障や企業活動、地域の安定性にも波及する大きな課題となっています。
そこで、このような課題への対応を目的として、2014年には、CEO Water Mandate、Alliance for Water Stewardship、CDP、Ceres、The Nature Conservancy、Pacific Institute、Water Footprint Network、World Resources Institute、WWFといった、国際的に影響力のある団体の代表者が集まり、水資源に関する連携と行動の必要性について議論が行われました。また、WWF(※1)が2020年に発表した『生きている地球レポート(LIVING PLANET REPORT)』では、世界の淡水生態系の豊かさが1970年と比較して84%も減少しているという深刻な事実も明らかにされています。この劣化のスピードは、陸域や海洋における自然の劣化を上回っており、特に淡水に依存して生息する野生動物のうち、約4分の1が絶滅の危機にあると言われています。
このように、水資源の持続可能な管理は、もはや一部の政府機関やNGOなどの団体の課題にとどまらず、市民社会が一体となって取り組むべき、地球規模の重要テーマとなっている状況です。そこで本コンテンツでは、水リスクに関する理解を深めるにあたり、まずは水リスクの定義を確認した上で、その種類や企業にとっての影響、企業がとるべき具体的な対応策について解説していきます。
(※1)World Wide Fund for Natureの略で、世界自然保護基金を表す。
目次
水リスクの定義と種類について
水リスクとは、企業や地域社会にとって、水に関連するリスク全般を指す概念で、大きく①物理的リスク、②規制的リスク、③評判上のリスクの3種類に分類されます。これらの水リスクは、それぞれが企業の事業継続性や信頼性に直結する要素となっています。とりわけ近年は、気候変動の影響が顕在化する中で、水に関する不確実性は増す一方です。そのため企業経営においては、リスクの把握とともに、科学的根拠に基づいた水資源マネジメントと、地域社会との協働が強く求められています。
そこで以下では、それぞれの内容と実際の事例を交えながら詳しく見ていきます。
① 物理的リスク
物理的リスクは、水の量や質、そして気象現象に起因するリスクを指します。主に、次の3つが代表的です。
- 水不足(量的リスク)
降水量の減少、地下水の枯渇、河川の干上がりといった要因によって、必要な水量を確保できなくなるリスクを指します。近年の代表的な事例としては、2018年に南アフリカ・ケープタウンで発生した「デイ・ゼロ(Day Zero)」が挙げられます。この都市では、異常気象や人口増加により深刻な水不足が発生し、全住民への水道供給が停止する恐れが現実味を帯びました。市当局は市民に対して1人あたり1日50リットル以下の使用制限を要請しましたが、これは米国の平均的な水使用量の6分の1程度に過ぎませんでした。そのため、もし供給停止が実現していた場合、1日25リットルという、たった4分間のシャワー分にも満たない水で生活をせざるを得ない事態になる状況でした。
- 水質悪化(質的リスク)
工場排水や農薬、生活排水などの流入によって飲料水や工業用水の安全性が損なわれるリスクです。典型例として知られているのが、インドのガンジス川です。この川はヒンドゥー教において「聖なる川」とされており、多くの巡礼者が沐浴を行いますが、その水質は極めて深刻な状態にあります。2017年の政府調査では、生活排水の未処理放出によって、場所によっては基準値の23倍もの大腸菌が検出されました。このような汚染は、飲用水の確保だけでなく、現地で事業を展開する企業の水処理コストを増加させ、持続可能な経済活動を困難にしている状況です。
- 洪水・異常気象リスク
洪水や豪雨などの異常気象などの気象現象に起因する水リスクを表しています。例えば昨今では、気候変動の影響で集中豪雨の頻度が増加しており、特にインフラの脆弱な地域では大きな被害が生じる機会が増えています。2011年にはタイで大規模な洪水が発生し、首都バンコク近郊に進出していた多くの日系企業の工場が浸水・操業停止に追い込まれました。損失は当時数十億ドル規模に上り、サプライチェーン全体に影響を及んでいます。また、近年の日本でも毎年のように大雨による洪水が発生しており、特に九州地方では河川の氾濫や土砂崩れによる住民避難や断水が相次いでいます。
② 規制的リスク
水資源の希少性が増す中で、各国の政府や自治体は水の利用や管理に対して法的規制を強化する動きを見せています。これが、規制的リスクです。
例えば、アメリカ・カリフォルニア州では、長期的な干ばつを受けて農業用水の使用制限が実施されました。これにより農家だけでなく、食品関連企業や流通業者にも大きな影響が出ました。また、水の使用料金が引き上げられたことで、企業にとっては運転コストの上昇につながっています。さらに、排水基準の強化により、排水処理施設への投資が求められる事例も増えています。もし企業の排水が基準を満たさない場合、操業停止や罰金の対象となる可能性もあり、事業継続に対するリスクは決して小さくないことがうかがえます。加えて、水資源の過剰使用が問題視される地域では、取水権の見直しや許認可の再審査が実施されるケースも出てきています。これらの状況からもわかるように、企業にとっては、安定的な水の確保が経営リスクとして浮上してきている状況であることが言えます。
③ 評判上のリスク
これは、企業の水使用や管理の姿勢が、投資家、消費者、地域社会、NGOなどのステークホルダーからの評価に影響を及ぼすリスクを意味します。例えば、企業が水を大量に使用して地域の水資源を枯渇させた場合、地元住民との摩擦が生まれ、抗議活動やボイコットにつながる可能性があります。実際に、南米ボリビアでは水道事業が外資系企業に民営化されたことに市民が反発し、2000年に「水の戦争」と呼ばれる大規模な暴動が発生しました。このような出来事は、企業にとって社会的信頼の失墜を意味し、ブランドイメージの毀損や市場での立場低下にも直結します。
このように、現代の企業には単に法規制を遵守するだけでなく、持続可能な水資源利用を実現するための積極的な姿勢が求められています。サステナビリティ報告書や統合報告書においても、水リスクに関する開示が常態化しており、企業は透明性をもって情報発信し、利害関係者の声に耳を傾ける姿勢が不可欠となっています。
企業にとっての水リスクの影響について
企業にとっての水リスクの影響は、第1章で述べたもの以外にも及びます。ここでは、資源調達に深く関係する業種において考慮すべき水リスクについて、サプライチェーン全体に渡って紹介していきます。
- 原材料調達への影響
水リスクが最も直接的に影響を与えるのが、原材料の調達段階です。特に農業、食品・飲料、繊維、製紙といった産業では、生産に大量の水を必要とする原材料を扱っており、水の確保が事業の根幹を支えています。このような業種では、干ばつや水資源の枯渇、政府による取水制限などが発生した場合、生産量の減少や調達の遅延、価格高騰などの影響を被る可能性があります。
実例として知られているのが、コカ・コーラ社によるインドでの地下水利用問題です。コカ・コーラは製品の製造において大量の水を必要としますが、地下水を汲み上げることによって周辺地域の水不足を招いたとして、地域住民から激しい反発を受けました。一部地域では抗議活動が拡大し、最終的には行政から操業停止命令が下される工場も出るなど、企業の信頼性と事業継続に当時、重大な影響を及ぼしました。このように、水資源をめぐる地域との摩擦は、企業活動の基盤そのものを揺るがす深刻なリスクになり得ます。
② 事業コストの上昇
水リスクは、企業のコスト構造にも影響を与えます。具体的には、水道料金の上昇、排水処理基準の厳格化、設備の改修・導入コストの増加といった形で、事業運営費が増大するリスクがあります。特に近年では、気候変動に対応する形で各国の規制が強化されており、企業にはより高度な水処理技術の導入や、モニタリング体制の整備が求められています。この負担は、特にインフラが未整備な地域での生産活動において顕著です。新興国や途上国では、行政による水インフラが十分に整っておらず、企業が独自に取水・排水施設を建設・運営しなければならないケースもあります。結果として、設備投資の初期費用や維持費が膨らみ、長期的な収益性に影響を与える可能性があります。
水の確保と環境保全の両立に向けて、企業には先進的な設備と管理体制への継続的な投資が求められる時代に入ってきていることがうかがえる状況です。
③ 投資・金融リスク
企業の水リスクへの取り組みは、投資家の評価にも直結する重要な要素となりつつあります。近年、ESG(環境・社会・ガバナンス)を重視した投資が拡大する中で、水の使用状況や水リスクに対する対応が、企業評価や投資判断の材料として注目されています。
例えばCDP(Carbon Disclosure Project)では、水セキュリティに特化した質問書を通じて、企業の開示姿勢と実行力を評価しており、優れた水管理を行う企業にはAスコアを与えています。このようなスコアは、グローバルな機関投資家の投資判断における参考指標として活用されることが増えており、水リスクに対する開示が不十分な企業は、資金調達の面で不利な立場に立たされることも予測されます。
また、ESG情報を金融商品の構成に活用する、サステナブルファイナンスが主流化しつつある今、企業には単なる法令遵守を超えた、積極的なリスク開示と持続可能な取り組みの実践が強く求められています。
④ 事業継続性への影響
水リスクは、突発的かつ甚大なインパクトをもたらす自然災害と直結しており、生産活動の一時停止や長期的な拠点移転、さらには地域社会との関係悪化など、様々な側面で企業の事業継続を脅かす存在となっています。
代表的な事例として、2011年にタイで発生した大規模な洪水が挙げられます。この災害では、多くの日系企業の製造拠点が浸水被害を受け、長期間にわたる操業停止や、世界中のサプライチェーンに深刻な遅延をもたらしました。特に自動車・電子部品業界では、生産計画の大幅な見直しを迫られ、数千億円規模の経済的損失が発生したとされています。
さらに、地域住民との信頼関係が損なわれた場合には、抗議活動や訴訟リスクに発展し、企業の社会的信頼を大きく傷つける可能性もあります。このような状況に陥らないためにも、水リスクを自然災害の一部として捉え、BCP(※2)に基づいた包括的な対応策を準備しておく必要があります。
(※2)Business Continuity Planの略で、事業継続計画を表す。
企業が取るべき対策について
ここまででお伝えしてきた水リスクに適切に対応するためには、以下のような戦略が必要であると考えられています。
- 水リスクの可視化と評価
企業はまず、自社の水リスクを正確に把握することが重要です。これには、使用水量の測定、リスクマップの作成、水ストレスの評価が含まれます。近年では、WRI(世界資源研究所)のAqueductツールなどを活用し、地域ごとの水リスクを分析する企業が増えています。 - 水資源の効率的な利用
技術革新を通じて、使用水量の削減やリサイクルを促進することが求められます。世界的な食品メーカーであるスイスのネスレ社は、水使用量削減のため、乳製品工場でゼロ・ウォーター技術を導入し、排水を再利用する取り組みを進めています。 - サプライチェーンとの連携
企業単体ではなく、サプライチェーン全体で水リスクを管理することが重要です。取引先や仕入先と協力し、節水技術の導入や水資源保全の取り組みを推進することが求められます。ドイツを代表するスポーツ用品メーカーのアディダス社は、製造パートナーと連携し、水使用量の削減を目的とした「DryDye技術」を採用しました。 - ステークホルダーとの協働
地域社会やNGO、政府機関と協力し、水資源管理の取り組みを強化することが求められます。特に、水ストレスの高い地域では、持続可能な水管理のためのパートナーシップが有効です。世界的な総合飲料メーカーのコカ・コーラ社はWWFと協力し、水源保全プロジェクトを展開しています。 - レジリエンス強化
企業は、水不足や洪水などのリスクに対する事業継続計画を策定し、異常気象に対する耐性を高める必要があります。世界中に日用品を提供する、アメリカのProcter&Gamble社は、自社の工場が洪水リスクの高い地域にある場合、予備の水供給設備を設置し、生産の安定性を確保しています。
まとめ
本コンテンツでは、水リスクに対する理解を深めるために、水リスクの概要から企業がとるべき具体的な対策までを解説してきました。
水リスクと向き合う上で最も重要なのは、企業が自社の事業特性や立地、サプライチェーン全体をふまえたうえで、的確なリスク評価と対応策を講じることです。水資源の持続可能な利用は、単なる環境配慮にとどまらず、企業の中長期的な競争力やレジリエンス強化にも直結します。ステークホルダーの信頼を得る上でも、水リスクへの戦略的な対応が今後ますます求められていくでしょう。
本コンテンツ、並びにCO2排出量の算定に関しご質問がございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。