Scope3(スコープ3)とは?Scope3(スコープ3)の全カテゴリ1~15と排出量算定のポイントを解説

温室効果ガスの排出量は、Scope1、Scope2、Scope3に分けて算定を行います。
その中でScope3(スコープ3)では、原料の調達、販売後の製品の使用、従業員の出勤、廃棄物の処理など、自社の事業や製品に関連して他社や個人が排出した温室効果ガスの量を算定します。
Scope3は15つのカテゴリに分かれており、Scope1、Scope2に比べると算定のハードルが高くなっていますので、まずは算定に向けて15つのカテゴリを理解すること、Scope3を算定するためのポイントを把握することが大切です。
この記事を通じて、温室効果ガス排出量算定のScope3について一つずつ確認していきましょう。
目次
- 1 Scope3とは原材料仕入れや販売後に排出される温室効果ガス
- 2 Scope3の各カテゴリ1~15の対象となるものの違いについて
- 2.1 カテゴリ1:購入した製品・サービス
- 2.2 カテゴリ2:建築物などの固定資産の建設・製造
- 2.3 カテゴリ3:ガス、電気などができる過程
- 2.4 カテゴリ4:サプライヤーから自社への物流
- 2.5 カテゴリ5:自社以外で処理をする廃棄物
- 2.6 カテゴリ6:従業員が出張で利用した鉄道や飛行機など
- 2.7 カテゴリ7:従業員の通勤
- 2.8 カテゴリ8:リース機器や賃貸オフィス
- 2.9 カテゴリ9:自社から卸先や消費者への輸送
- 2.10 カテゴリ10:製品の購入先企業での加工
- 2.11 カテゴリ11:販売した製品の使
- 2.12 カテゴリ12:販売した製品の廃棄
- 2.13 カテゴリ13:他社にリースした製品
- 2.14 カテゴリ14:フランチャイズ店での排出
- 2.15 カテゴリ15:株式投資や債券投資などの運用
- 3 Scope3を効率的に算定する4つのポイント
- 4 まとめ
Scope3とは原材料仕入れや販売後に排出される温室効果ガス
Scope3(スコープ3)はScope1、Scope2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)”と定義されています。
温室効果ガス排出量は、Scope1、Scope2、Scope3に分かれ、Scope3では、Scope1とScope2に該当せず、自社の事業や製品に関連して他社や個人が排出した温室効果ガスの量を算定します(間接排出と言います)。
例えば、算定する事業者が冷凍野菜を製造、販売している企業だと、下記などをScope3で算定します。
- 農家が野菜を栽培する過程で排出した温室効果ガス
- 他社のトラックが野菜を自社工場に運んできた際に排出した温室効果ガス
- 冷凍野菜を購入した消費者がガスコンロで調理した際に排出した温室効果ガス
製品に関わることだけでなく、従業員の移動、廃棄物の処理、賃貸オフィスの利用などを算定する項目もあります。
サプライチェーンの「上流」と「下流」から排出されるGHGを対象とする

SCOPE3は、主に上流SCOPE3と下流SCOPE3に分けられます。上流SCOPE3は、企業がサプライチェーン全体でどれだけのGHGを排出しているかを理解し、サプライチェーンの持続可能性を評価する上で重要です。一方、下流SCOPE3は、製品やサービスのライフサイクル全体での環境への影響を理解するのに役立ちます。
カテゴリで分類すると自社が製品やサービスを生産する前に排出された温室効果ガス(Scope3カテゴリ1~8)が上流、自社が製品やサービスを販売した後に排出された温室効果ガス(Scope3カテゴリ9~15)が下流となります。
では具体的にスマートフォンの製造を考えてみましょう。スマートフォンメーカーが自社製品のGHG排出を評価する場合、上流SCOPE3には以下のような要素が含まれます。上流SCOPE3
原材料調達:スマートフォンの製造には、多くの希少金属やプラスチックなどの原材料が必要です。これらの原材料の採掘や生産過程でGHGが排出されます。例えば、鉱山でのエネルギー消費やトランスポートによる排出が考えられます。
部品製造:スマートフォンには様々な部品が組み込まれています。これらの部品の製造プロセスでもGHGが排出されます。例えば、電子部品の製造にはエネルギーを消費するプロセスが含まれ、これによりGHGが発生します。
製造プロセス:スマートフォンの組み立て工程では、様々な工程でエネルギーが使用されます。これにより、GHGが排出される可能性があります。
下流SCOPE3
製品使用時のエネルギー消費:スマートフォンの使用中に、データ通信やアプリの利用などにより電力が消費されます。この電力の供給には、発電プロセスに伴うGHG排出が関与します。
廃棄物処理:スマートフォンが廃棄されるとき、適切な処理がされない場合には環境への悪影響が発生します。廃棄された電子機器からの廃棄物処理により、有害物質やGHGが排出される可能性があります。
製品の再利用やリサイクル:スマートフォンの再利用やリサイクルは、GHG排出を削減するための有効な方法です。再生可能な部品や材料を使用することで、新たな原材料の採掘や製造に伴うGHG排出を削減することができます。
上流SCOPE3と下流SCOPE3の両方を考慮することで、企業は製品のライフサイクル全体での環境への影響をより包括的に理解し、現状の即したGHGの算定が可能となります。Scope3は、上記のようなシチュエーションに応じて15種類のカテゴリに分かれています。各カテゴリについては、次の章でご説明します。
Scope1やScope2との違い
| Scope | 概要 |
|---|---|
| Scope1 | 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス) |
| Scope2 | 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出 |
| Scope3 | Scope1、Scope2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出) |
Scope1、Scope2、Scope3は上の表のように分けられます。Scope3に該当する温室効果ガスを理解するには、Scope1とScope2に該当する温室効果ガスも正しく理解する必要があります。
Scope1は、事業者が事業活動の一環でガスやガソリンなどを使い、排出した温室効果ガスが当てはまり、具体例としては、下記などが当てはまります。
- 事業者が飲食業で、店内のガスコンロで調理をした
- 会社の営業車を使って営業活動を行った
- 自社工場での製品の製造過程で火を使用した
一方で、Scope2は、事業活動の中で電気、熱、蒸気などを使用した際に発生する温室効果ガスで、下記などが当てはまります。
- 自社オフィス内での電気の使用
- 全国各地の支社(支店)のオフィス内での電気の使用
Scope1、Scope2について詳しくは、下記のページでご説明していますのでご参考ください。


Scope3の各カテゴリ1~15の対象となるものの違いについて

画像は、Scope1、Scope2、Scope3の全体図です(スマホで見づらい場合は、拡大してご覧ください)。
Scope3が15種類のカテゴリに分けられると前の章でご説明しましたが、画像のようにシチュエーションに応じて細かく分けられます。
この章では、各カテゴリの概要をご説明していきます。
なお、カテゴリごとの詳しい情報は、リンク先のページでご覧いただけます。
カテゴリ1:購入した製品・サービス
Scope3カテゴリ1では、自社製品の製造や自社の運営のために購入した物品が作られた段階での温室効果ガス排出量を算定します。家電メーカーがネジを仕入れた場合、ネジが製造される過程でも温室効果ガスは発生しています。これを算定するのがカテゴリ1です。 製品を入れる段ボールやビニール袋なども、外部企業から購入していれば、カテゴリ1の対象となります。また、クリーニングやレンタルサーバーといったように、形のないサービスもカテゴリ1の対象となります。
カテゴリ1について詳しくはこちらをご確認ください。

カテゴリ2:建築物などの固定資産の建設・製造
Scope3カテゴリ2では、自社ビルなど、長く使用する資産を建設、修理した際や、購入した資産の製造段階で発生した温室効果ガスが該当します。代表的なのは自社ビルや工場の建設・修繕ですが、建物だけでなく、トラックやフォークリフトなど、財務会計上で固定資産に該当するものが当てはまります。また、ソフトウエアのような長く使う無形物も該当します。
カテゴリ2について詳しくはこちらをご確認ください。

カテゴリ3:ガス、電気などができる過程
Scope3カテゴリ3では、ガスや電気など、使用したエネルギーの採掘や輸送の段階で発生した温室効果ガスの排出量を算定します。しかし、自社で使用したエネルギーの採掘や輸送をどの企業が行っているか、ほとんどの事業者が把握していないと思います。そのため、カテゴリ3は事業者のエネルギー使用量や金額から温室効果ガス排出量を算定します。
カテゴリ3について詳しくはこちらをご確認ください。

カテゴリ4:サプライヤーから自社への物流
Scope3カテゴリ4で算出するのは、サプライヤーから製品や原料などを購入し、自社の工場、店舗などに輸送した際に発生する温室効果ガスの排出量です。カテゴリ4に該当するのは、他社の配送サービスを利用した場合で、自社で所有するトラックなどで運んだ際はScope1やScope2で算定します。また、輸送だけでなく、自社に運ばれるまでの荷役や保管で発生した温室効果ガスも算定の対象です。
カテゴリ4について詳しくはこちらをご確認ください。

カテゴリ5:自社以外で処理をする廃棄物
Scope3カテゴリ5はゴミの処分です。ほとんどの事業者はゴミの処理を外部企業に依頼していると思いますが、ゴミ処理業者が輸送や処理の際に排出した温室効果ガスはカテゴリ5で計算します。一般的な事業ゴミだけでなく、リサイクル、産業廃棄物の処分も算定の対象です。
カテゴリ5について詳しくはこちらをご確認ください。
カテゴリ6:従業員が出張で利用した鉄道や飛行機など
Scope3カテゴリ6では、従業員の出張に伴う温室効果ガスの排出を算定するカテゴリで、出張での鉄道、飛行機、バス、タクシーなどの利用が対象となります。算定は交通機関が公表する情報から算定する方法の他に、支給した交通費や出張日数など、自社が所有する情報だけで算定する方法もあります。なお、自社の営業車で出張した場合は、カテゴリ6ではなく、Scope1またはScope2が当てはまります。
カテゴリ6について詳しくはこちらをご確認ください。

カテゴリ7:従業員の通勤
Scope3カテゴリ7では、従業員が通勤で利用している電車、バスなどの温室効果ガス排出量を算定します。自家用車やバイクで出勤している場合も対象です。カテゴリ6と同じように、支給した交通費から算定することも可能です。なお、テレワーク時に従業員が自宅で排出した温室効果ガスもカテゴリ7に該当しますが、2023年3月時点では任意算定対象となっています。
カテゴリ7について詳しくはこちらをご確認ください。

カテゴリ8:リース機器や賃貸オフィス
Scope3カテゴリ8では、事業を行うために他社からリースしている物品を使用した際に排出した温室効果ガスが対象です。リースしているパソコンや複合機などの使用が代表的で、物品だけでなく賃貸のオフィスや店舗も該当します。ただし、これらはカテゴリ8ではなく、Scope1やScope2で算定することが実際には多くなっています。
カテゴリ8について詳しくはこちらをご確認ください。

カテゴリ9:自社から卸先や消費者への輸送
Scope3カテゴリ9では、自社の製品を販売した後の輸送や配送に伴う温室効果ガスの排出量を算定します。販売後の輸送の全てが対象ではなく、購入相手が輸送の費用を負担した場合、購入相手が所有するトラックなどで輸送した場合がカテゴリ9の対象となります。自社トラックでの配送や自社が費用を負担しての配送は、カテゴリ9では算定しません。また、輸送だけでなく、その後の保管や販売も対象となります。例えば、購入後に卸先の倉庫で保管されていた場合、卸先が販売する際に電気などを使用していた場合(自社製品が冷凍食品で、冷凍庫を使用したなど)が当てはまります。
カテゴリ9について詳しくはこちらをご確認ください。

カテゴリ10:製品の購入先企業での加工
Scope3カテゴリ10は、販売した製品の加工に伴う温室効果ガス排出量を算定します。中間製品を販売する事業者は算定が不可欠のカテゴリです。自社の製品が購入先企業で多数の商品に使われている場合(生地メーカーがアパレルメーカーに生地を販売した場合など)は、算定に大きな労力を必要とすることもあります。
カテゴリ10について詳しくはこちらをご確認ください。

カテゴリ11:販売した製品の使
Scopeカテゴリ11は、販売した製品を購入者が使用した際の温室効果ガス排出量を算定します。自動車のように製品自体が温室効果ガスを排出する場合だけでなく、フライパンのように温室効果ガスを排出する製品(フライパンであればガスコンロ)と一緒に使う場合も対象です。なお、購入者が商品を実際に使用した回数や時間を把握して算定することは難しいため、定められた計算式を用いて温室効果ガスの排出量を算定します。
カテゴリ11について詳しくはこちらをご確認ください。

カテゴリ12:販売した製品の廃棄
Scope3カテゴリ12では、事業者が販売した製品の処分や、リサイクルに出された際の温室効果ガスを算定します。製品以外に梱包していた段ボールやトレーの廃棄もカテゴリ12に含まれます。例えば、事業者がスーパーマーケットで、お刺身を販売した場合、お刺身は食べてなくなりますが、販売時に入れていた容器は処分することになり、これも算定の対象となるというわけです。算定時には、製品ごとに発生する廃棄物をリストアップし、それぞれ算定していきます。
カテゴリ12について詳しくはこちらをご確認ください。

カテゴリ13:他社にリースした製品
- オフィス機器のリース
- 営業車など企業向けの自動車のリース
- 事業用テナントの賃貸
Scope3カテゴリ13は、事業者が他社や消費者に対して製品のリースを行い、その製品が使われた際に出る温室効果ガスの排出量を算定する項目です。リースには、オフィス機器や自動車などのリースの他、事業用テナントやマンション、アパートの賃貸も含まれます。製品ごとのエネルギー消費量から算定し、不動産の場合は建築物の床面積から算定することもできます。
カテゴリ13について詳しくはこちらをご確認ください。

カテゴリ14:フランチャイズ店での排出
カテゴリ14は、フランチャイズ店が営業の際に排出した温室効果ガスを算定する項目です。フランチャイズ展開している飲食業などは算定する必要があります。フランチャイズ展開していない事業者は算定が不要のことが多いです。
カテゴリ14について詳しくはこちらをご確認ください。
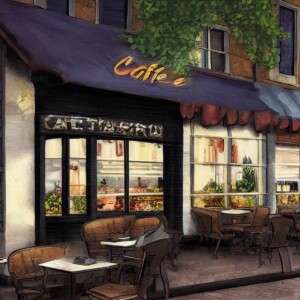
カテゴリ15:株式投資や債券投資などの運用
Scope3カテゴリ15は、投資に関連して発生した温室効果ガスを算定する、民間金融機関(商業銀行など)向けのカテゴリです。投資事業を行っていない事業者は算定不要のケースが多いです。また、投資を行っている企業であっても、投資に関わる温室効果ガス排出量はScope1やScope2で算定し、カテゴリ15では算定しないケースもあります。
カテゴリ15について詳しくはこちらをご確認ください。

Scope3を効率的に算定する4つのポイント
ここでは、Scope3の各カテゴリを算定するために抑えておきたいポイントを解説していきます。
当サイトが考えるポイントは、上の4つです。
算定対象を整理する
Scope3のカテゴリごとに、自社の事業の中で該当する製品、店舗、社員などを整理していきましょう。
例えば、家電メーカーであれば、1つの電化製品に対し、原材料の仕入れから製品の使用、廃棄までの流れを視覚化して温室効果ガスの排出量を確認していきます。製品が多い、従業員数が多い企業では、とても労力を必要とする作業ですが、はじめにしっかり整理して算定を行った方が、後々の作業がスムーズに運ぶでしょう。また、初年度にしっかり整理しておくことで、翌年以降の算定の負担が軽減されます。
協力してもらう社内各部署の理解を深める
算定で大事なのは、必要なデータを収集することです。
データは外部企業と社内からそれぞれ入手することになりますが、外部企業から入手できるデータには限りがあり、社内で入手できるデータを代用して算定を行うケースも多いです。そのため、温室効果ガスの算定には社内の各部署の協力が必要不可欠です。しかし、他部署の方々も忙しいですし、なぜ、温室効果ガスの排出量を算定でデータを提供する必要があるか理解していないこともあります。また、部外秘の情報で提供を拒否されることや、作業が手間で後回しにされることもあり得ます。
このような状況の時は、なぜ自社で温室効果ガス排出量の算定を行っているのか、算定することで会社にどのようなメリットがあるかを伝え、社内の理解を深めていきましょう。データをもらうことも大事ですが、協力してもらうための社内での根回しも同じぐらい大事です。
無理のない算定をする
温室効果ガスの排出量は、最初から完璧な算定を目指す必要はありませんし、外部企業のデータが揃わない場合などは、簡易の計算式で算定しても全く問題はありません。
初年度はできる範囲で算定を行い、社内で算定のフローや協力体制を確立していき、年数を重ねるにつれて徐々に確度の高いデータにしていくことを目標にしましょう。また、任意算定項目まで全て算定しようと考えなくて良いでしょう。
GHG排出量の算定ツールを利用する
算定が多岐にわたる事業者では、自分たちだけで算定を長く継続していくには膨大な労力を必要とします。現在は、GHG排出量の算定ツールや算定をサポートする専門サービスが多数あり、外部サービスを利用して効率的でより正確な算定を実践することが可能です。入手したデータを必要な場所に入力するだけで、計算を自動で行ってくれるツールも多く、合わせて専門家のサポートを受けることも可能です。導入を検討する際には、実務的な利便性や付属する機能などを比較するのが良いでしょう。Excelライクな入力機能で操作性が高く、算定結果のレポートを要望に応じてカスタマイズできる「CARBONIX」がおすすめです。
温室効果ガスの算定は、この先、何年、何十年と続ける可能性がありますので、早い段階で外部サービスを導入し、外部サービスを使用した社内の算定フローを確立させましょう。
まとめ
温室効果ガス排出量を算定する際のScope3についてご説明いたしました。Scope3では、Scope1とScope2に当てはまらない温室効果ガスの排出を算定します。15つのカテゴリに分かれていますので、まずは各カテゴリの概要や当てはまる例題を把握しましょう。そして、実際に算定する際は算定のポイントをぜひご参考ください。
Scope3は、Scope1、Scope2よりも算定が難解なことが多いため、Scope3に該当する温室効果ガスの算定には、GHG排出量の算定ツールなどを活用することをおすすめします。また、本サイトでは、Scope3の各カテゴリについて、詳細にまとめたページを用意していますので、特定のカテゴリを詳しく知りたい時などにご参考ください。






